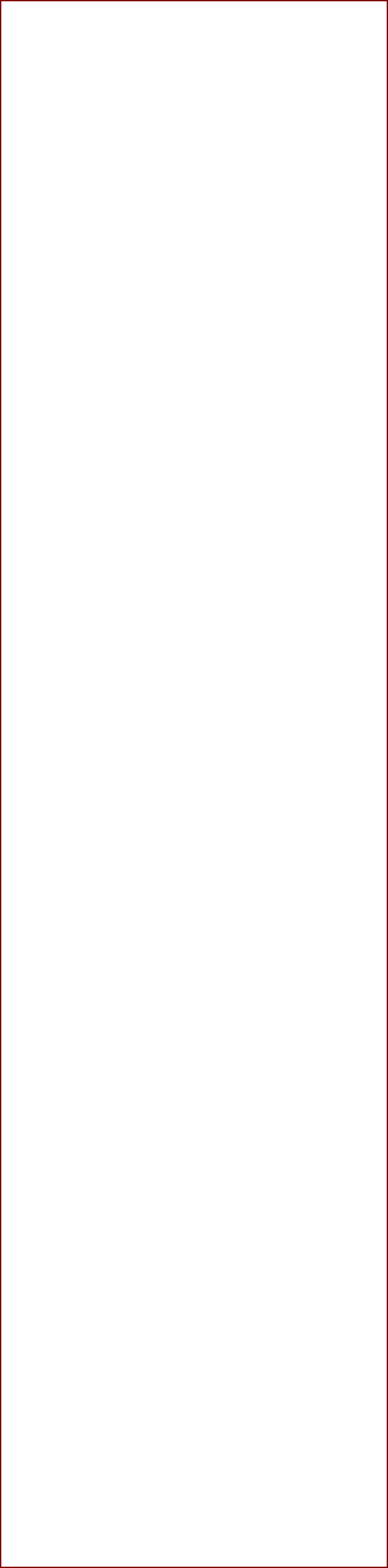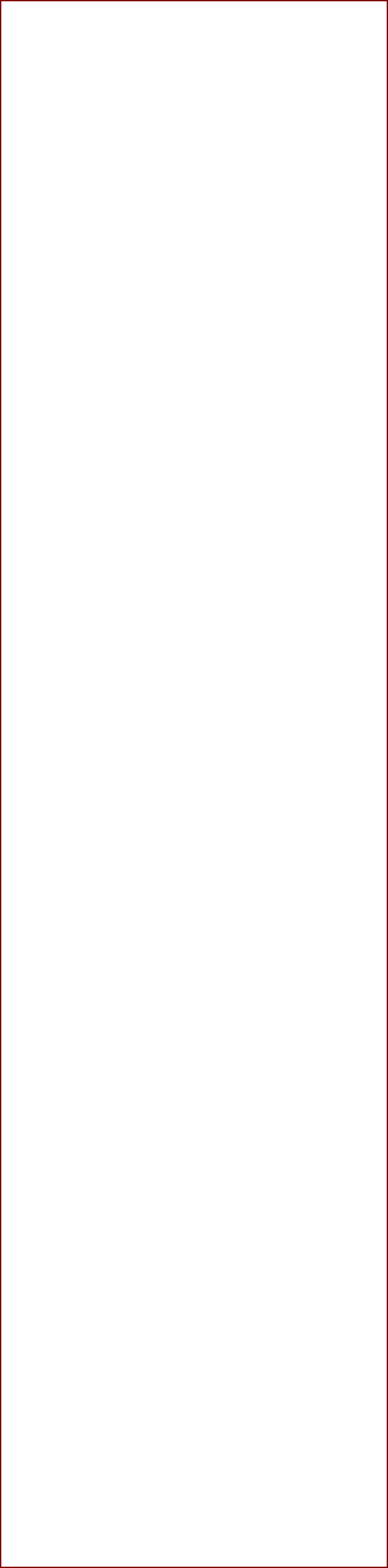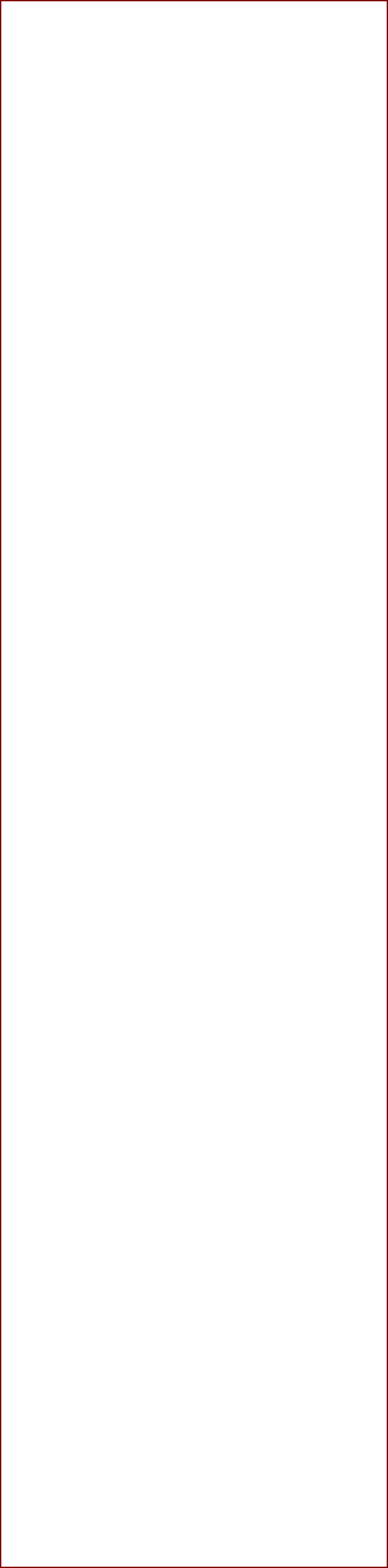
「白衣の仁王」 ‥‥花弓留朗の日記から
その日は朝から薄暗く、まるで夕暮れのようでありました。
灰色の分厚い雲がぎっしりと空を覆っていて、昼間であるというのに街灯には明かりがついておりました。
そんな日の午後、十才になる私は父に連れられて町外れの小さな病院へとやってまいりました。
あちらこちらの家々から漏れる明かりを眺めながら歩くうちに、気が付くと『酒手医院』と書かれた看板の前にたどり着いており ました。
「ここだ」と父は言い、さっそく私達は玄関へと回りました。玄関は隣の家との間を入った薄暗がりにあり、こんな日だと言うのにドアの上の電灯はついておりません。
私は思わず父の手をギュッと握りその後ろに隠れました。
それと同時に父の手がすーうっと伸び、埃だらけになったブザーを押そうとしました。
と、突然私は父の手を引きながら叫んでしまいました。
「帰ろうよ、お父さん!帰っていいんだって」
すると父は私の言葉をつぶすように
「何を訳の分からないことを言っているんだ」
「だって、ほら、看板に書いてあったよ」
「あの看板がどうしたんだ」
「サケテ、避けていいんだって、だから帰ろうよ」
「馬鹿、これは『酒、手』と書いて、さ、か、て、と読むんだ」
父はそう言い終わると玄関ブザーを押しました。しかしブザーは直ぐには鳴らず、
父が何度か押すうち、まるで鳴きつかれた晩秋の虫のようにやっとのことで鳴りだしました。
ジッジー、ジジッジー‥‥。
するとこの日の空模様みたいな低く重い「 はい ‥‥」という声。
「おう、わしだ、花弓だ」と父が答えるのを聞いて、私はこの二人が友達だと知り、思わずほっと胸を撫で下ろしました。
さて、中に入りますとそこは普通の家と同じような造りになっており、二人は靴を脱いで一段上がり、父に薄っぺらい茶色のスリッパを履かされました。
ペタペタ、ペタペタ
十才の私にはまだ大きすぎるスリッパの鳴り響く音が、受付も看護婦もいなく廊下の電気も節約された閑静な病院の中に吸い込まれていきます。
ガチャッ!
丸い真鍮の取っ手を回してドアを開けると、診察室の中はガラーンとしています。
そしてそこには座高が高くガッチリした男が、浅黒い顔には似合わない白衣をまとい、肘掛けのある椅子に腰掛けております。
そいつが無理に頬を持ち上げるように微笑み、やや儀礼的に「 やあ 」と父に声をかけると、
父親も「 よぉ 」と伏目がちにやや押さえた声で挨拶を交わしました。
予想外に距離を保った二人の態度に、私は思わず不安を感じました。
私は直ぐに患者用の貧弱な丸椅子に腰掛けさせられました。見上げるとそこには四角い顎の上に大きくどっしりとした鼻が陣取っております。
「で、どんな具合で?」
「手が水や湯に濡れると痒いらしく、柱や机にガリガリこすりつけて、血が出るまでやっている」と父。
「フーム」と医者は言ったきりしばらく黙ってしげしげと観察し始めました。
しかし、眼は真剣そうにしているのですが、鼻の小脇が小さく吊り上がり、
私の手をまるで汚れ物でも掴むかのように、そおっとけげんそうに触るのであります。
私はいつも学校で掃除当番の時などホウキの係ばかりやっていました。
それは雑巾掛けをやると後で手が痒くてたまらないからです。
しかし冬などは他の生徒からは「楽な方だけ選んでいる」と白い眼で見られておりました。
私がそんなことを思い起こしていますと、突然その先生はスックと立ち上がり、「注射を打つ!」と。
その急で断言的な言い方の中に格好をつけたものがあるのと、注射という言葉を聞いて私はがっかりしてしまいました。
「そこのベットで尻を出して寝て」
「はい」と、私はぼんやりと答え、諦めてトボトボとベッドへ。
「早く尻を出して」
ハッと振り向くと、そいつは既に注射器を持ってそばに立っております。
「は、はい。」
私はその素早さに驚きあわててズボンを降ろし、ベットに上がろうとしました。背中にため息混じりの威圧的な気配を感じながら「 いよっ、ひょっ 」と掛け声をかけながら幾度も試みるのですが、どうしてもベッドに上がることは出来ません。
気が付くとそのベッドが子供の私には高い上に、膝まで降ろしたズボンの為に私は胴長短足状態だったのであります。
「いよっ」。
結局私は一旦ズボンを上げてベットに乗り、それからシャクトリムシが進むみたいに尻をあげながらパンツとズボンを降ろしたのであります。そしてあわてていたのでベッドの端ギリギリに寝てしまったのであります。すると医者は待ちかねたようにすかさずアルコールで右尻を拭きました。
涼しくなった右尻に次ぎに襲ってくるであろうはずの痛みに私はグッと構えました。
ところが一向に針を刺す気配がやって来ないではありませんか。
私は不審に思い、無理して首を左へ捻り医者を仰ぎ見ました。 ところが唖然、愕然、呆然!
何とそいつは注射器を逆手に持ち、彼の頭上高くそれを振り上げているではありませんか。
頭にはあの医者専用の穴開き凹面鏡がキラリと光っており、鼻穴も全開。
その姿はどこぞの仁王像そのもの。
それを見た花がワッと驚き飛び上がると同時に間髪いれず「 フンッ 」という呼吸音。
注射器はまるで殺人鬼の出刃包丁の如く振り下ろされたのであります。
「ワッ!」 ブスッ。
驚きあわてた花の左腕ははずみでずり落ち、空を切ってべッド下へ回り込み、その勢いで体半分は落ちかけ、咄嗟にベッドにしがみついたのであります。
そして当然のこと、私の右尻は注射針を握り締めるが如く異常に緊張したのであります。
「尻の力を抜いて、尻の力を抜いて」と白衣の仁王。
かくて注射液は強行に私の体内に侵入して来たのであります。
と、どうでしょう何故か右尻が私の意に反して勝手に力を抜こうとするのであります。
何というか、くねぇーとした感じ。
ああ‥‥、緊張と切なさの葛藤状態。
すると今度は山を登って下る時の『 脚が笑う 』というのと似たような『 尻が笑う 』
そんな感じが襲ってくるではありませんか。
「お、‥‥落ちる」
左脚はすでにぶら下がって宙ぶらりん。しかしこれがまた不可解、笑う尻のせいでありましょうか、
花はこんな姿になった自分が、ふとおかしくなったのであります。
笑うと力が抜けて益々落ちそうになり、それで慌ててまたベットにしがみつく。
だが、皮肉な定めと申しましょうか。
堪えれば堪えるほどに笑いは込み上げて体は揺すれてしまうのであります。
「力を抜いてっ、尻の力を抜い‥てぇっヘッヘッヘッ‥ウックックーッ」
ついに仁王もつられて笑い出しました。
それまでムスッとして保っていた医者の威厳も崩れ去り、もう取り返しがつきません。
二人とも益々笑いが止まらなくなり、仁王の手の力も抜けて注射液も一向に浸入して来れません。
花の右手はズルズルとベッド上を中央へ移動し、ついに体まで宙ぶらりんとなったのであります。
やっと注射器が目的を遂げ、花の体から去ってゆくと、花は床へドタッ。
「よく尻を揉んでっ!」と、すかさず威厳を取り戻そうとする仁王の威張った口調と、父親に尻を揉まれる度に味わう脱力感混じりの痛み、又しても花は笑いが止まらないのでありました。
この一幕のお陰で注射に伴う痛みは殆ど感じないで済んだことは幸いなことでありました。
やはり苦しいときには笑うと良いのでありましょうか。
帰り際、玄関のスリッパ棚の上の小さな受付窓から低い声で、
「はい、カユミトメロウ君、痒み止めを出しておきます」
と真面目な口調の仁王。すると父は訊ねたのであります。
「どうだ何か分かったか」
「いや、よう解らんからペニシリンを打っておいた」
花はこの過去をしみじみと顧みて二句吟じたのであります。
薬より 効く薬知り 笑う尻
お尻さえ 笑ってこらえる 注射かな
---------------------------------------------------------------
.
えっ?注射はきいたかって? 効きませんでした。笑いすぎたのがいけなかったのでしょう。