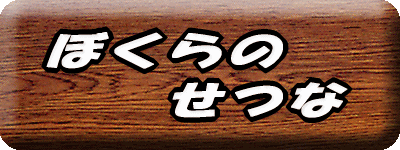
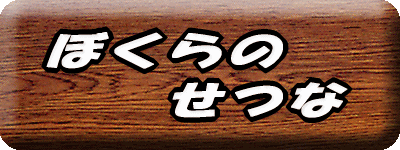
「今夜、泊まれよ」
背中を向けたまま唐突に祐希は言った。
あまりに思いがけない申し出だったから、とっさに即答出来ずに口篭もった。それが優柔不断を嫌う弟の機嫌を損ねた
かとも思ったが、祐希は無言のまま昴治の頼み事の消化に勤しんでいた。
「いいけど---どこに寝ろっていうんだよ」
慌てて、それでも軽口に聞こえるようにと願いつつ言葉を継いだ。頭の中にはぐるぐると---何故急に?どうして?---同
じ疑問が巡っていた。
「・・・昔みてえに」
まるで罪の告白のような弟の弱々しい声音。
そうだな、と何でもない振りで答えながらコーヒーカップを手渡せば、祐希は一瞬窺うような視線で昴治を見上げた後、
「あんたの寝相じゃ、蹴り落されるのがおちかも知れねえけどな」
いつもの仏頂面に戻って言い放つ。
「---お前に言われたくないぞ」
今度は振りでなくむっとして言い返した。祐希は何も反論しなかったが、その横顔は穏やかに笑んでいた。
何なんだよ、もう---無意識の口癖を胸中に落とし、それでもどこか弟の笑顔にほっとしている自分を訝しんだ。
どんな心境の---しかも劇的な---変化があったのだとしても、祐希が自分に歩み寄ろうとしてくれている。その事実は
昴治にとって歓迎すべきことであるし、素直に嬉しいと思う。
なのに---拭えないこの一抹の不安はなんなのだろう。
「おい、ここまで下らねえ質問にも答えるのか」
有り有りと呆れた口調に思惑の淵から呼び戻され、どれどれとモニタを覗いて見れば、
「・・・いっぱいあるから嫌なのは飛ばしていいよ。どのみち全部やることないし」
そこにあったのは、到底女性が書いたとは思えない---というより思いたくない、悪戯かセクハラ紛いの問いの羅列。
弟の言の正しさに思わず目を覆って、昴治は溜息とともに少し冷めたコーヒーを啜った。
その夜、5年近い時間を隔てて2人は同じベッドに眠った。
細身とはいえ成長期の男同志であるから、シングルベッドに収まる為にはぴたりと身体を寄せなければならず、昴治は
押しやられた壁際に顔を向けて上掛けを被ったが、灯りを消した祐希は隣に滑り込んでくるとほとんど同時に、後ろから
腕を回して兄の身体にしがみ付いてきた。
いや、それはそんな子供じみた行為などではなく、むしろ「抱き締められている」といっていい有様に思えて。
馬鹿馬鹿しい。そう考えながらも、昴治はこの事態でなら当然口にしていい筈の---「鬱陶しいから離れろよ」---台詞
1つ発することも出来ないまま夜を過ごした。
まるで罪の告白のような---
先刻弟の物言いをそんなふうに感じた事をふと思い出し、全身に形容し難い衝動が走るのを耐えたりもした。今は笑顔
を絶やさない親友の、あの「終幕」間際に見た苦渋に満ちた表情が脳裏を掠めたからだ。
馬鹿馬鹿しい。もう一度胸に繰り返し、昴治は硬く目をつぶる。
たったこの前まであれほど祐希に嫌われていたくせに。
リヴァイアス内は勿論、外の世界にまで数多の女性信奉者を持つ弟に対する、おそらくは最大限の侮辱に他あるまい、
いま昴治がした想像など。
本人が知ればきっと烈火の如く息巻いて、今更にでも拳の1つくらい食らわされるかもしれない。それよりもあの侮蔑を
込めた冷たい眼差しで嘲笑されるのがおちだろうか。
どちらにしても、有り得ない取り越し苦労ではあるけれど。
(お前だって悪いんだぞ。手のひら返したみたいに急に、でかい図体して紛らわしいコトするから・・・)
知らず強張っていた身体の力を抜いて、昴治は自然に弟のもたらす温もりに身を預けてみる。あっという間に兄の背を
追い越した礼儀知らずの胸は、思っていたよりも広く不思議なほど居心地が良かった。
(やっぱりこれって、甘えられてる・・・んだよな?)
腰の辺りに置かれた自分より大きな手に、そっと手のひらを重ねてみた。まだ眠りきってはいなかったのか、祐希は僅
かに身じろいで、けれど無言のまま尚更に身を寄せてきた。
「---おやすみ、祐希」
ベッドに入る前口にしたことを昴治はもう一度声に出して言った。思った通り弟の応えはない。
唐突に昴治は、振り向いて祐希を正面から抱き締めてやりたい衝動に駆られた。
どうしてか、応えない弟が夢に怯えて泣いているような錯覚に囚われて、随分と永い間、昴治は暗闇の中眠れずに耳を
すませていた。
「おはよう、祐希くん。ご機嫌はいかが?」
翌朝のリフト艦で祐希が最初に行き合ったのは、何時にも増してテンションの高い所属課班長の胡散臭い笑顔だった。
常の通り返事も返さず自席についた。普段であれば「愛想がない」やら「ノリが悪い」などとボヤくに留めて、早々に離れ
ていくイクミだが、
「悪いわけないですよね。夕べの出来事のアトだもの」
シートの後ろまでついて来たと思えば、訳知り顔を緩ませて馴れ馴れしく祐希の肩に両手をポンと乗せ、しきりに頷きを
繰り返す。
その手を乱暴にはらって、祐希は見慣れた澄まし顔を睨め上げた。昴治が昨夜祐希の個室を訪れたことも、その理由
までもをイクミは知っている。何かにつけて兄をネタに祐希をからかうこの男が、昨夜のことを取り沙汰しない筈はないか
ら何時ものことと放っておけばいいものだが、
「何が言いてえんだ、気色悪ィ」
兄に対する想い故、その後ろめたさを逆なでされて、知らず零れた声音は自分でも呆れるほどに低く尖っていた。
戦友のそんな非友好的な態度に、しかしイクミは少しも動じる様子など見せず、
「朝、カフェで昴治に会ったんだけど。すごく---何ていうか、嬉しそうでさ。どうしたのか聞いても教えてくれなくて、でも
一言だけ「夕べ、信じられないくらい良いコトがあった」って」
自分の方こそが幸福そうな、滅多に浮かべない柔らかな表情で微笑った。
「・・・ワケ分かんねえよ」
次に発した台詞はぎこちなく小さく響いた。心底兄を思いやるイクミの情に気圧されて、祐希は逃れるように目線を端末
の上に落した。
その仕草を照れ隠しとでもとったのか、「まあまあ」と再び祐希の肩を軽くたたき、イクミは上機嫌のままブースを離れて
行った。
ほっと息をつきながら、お節介なチームリーダーの言を反芻する。胸に湧き上がるのは兄を喜ばせた満足感と、同じ強
さの脱力感。
(あんなことで、あの激鈍の大ばか野郎に解からせられるとは、思っちゃいねえけど---)
次々にスタッフが入室して来た。隣のブースからカレンが挨拶を寄越すのに適当な相槌を返しながら、祐希はミッション
開始を告げるイクミを盗み見た。
命を賭けた確執の果て、今や自分以上に昴治を大切に思う目前の男は、祐希の不埒な望みを知った時はたしてそれを
許すだろうか。
己の過去に頗る傷付いたイクミであればこそ、兄に同じ轍を踏ませることを良しとするとは思えなかった。
勿論だからといって諦めるつもりがあるわけではなく、誰の許可を貰おうとも、まして得られるとも考えてはいない。
祐希の想いを咎めることが出来るのは、この世でただ1人---それを向ける先である兄、昴治本人だけなのだから。
祐希のIDカードが目覚まし代わりのアラーム音を発した時、腕の中の兄はまだ眠りの中にいた。急ぎ設定をオフにして
そっと抱擁を解き、名残惜しさを振り切ってベッドを降りた。
寝起きの悪い弟とは正反対に時計のベルの最初の一音で目を覚ませる昴治だが、昨夜の寝つきが大層遅かった為だ
ろう、今朝はアラームに反応一つ見せぬまままどろみ続けている。
ベッドヘッドに作り付けられているタイマーを兄の出勤に充分間に合うはずの30分後にセットしてから、祐希は手早く身
支度を整え1人自室を後にした。
ほぼ5年振りの兄との夜を祐希は、一睡もしないまま過ごした。
眠れなかったわけではない。ただ噛み締めることに夢中だったのだ。兄の温もりや感触、仄かに甘く感じられた匂いや
唇から洩れる吐息の一つまでもを。
ベッドの中で背後から自分を抱き締めた祐希の手に、昴治がおずおずと手のひらを重ねてきた瞬間、かっと全身の血
が沸騰したような錯覚に陥った。
獣じみた欲求を捩じ伏せたのは理性などではなく、いま事を起こすのは早計だと思惑を巡らせたからだった。
まだ早い。祐希の行為をおそらくは弟の甘えと断じて許したに違いない、ただ兄でしかない昴治には。
今朝顔も合わせないまま部屋を先に出たのも、気を引く手管の1つだった。
強引に近付いてみせながら、ふいに素気無く距離をおく。時に頑固なほど真っ直ぐで単純な兄だから、弟のそんな態度
にきっと冷静ではいないだろう。
(掻き回して、混乱させて---そこに付け込む、ってのもアリか)
午後の講義へと向う道すがら、頭をかすめた我ながら卑屈な思考に、祐希の頬に自嘲の昏い笑みが浮かんだ。
「---祐希?」
まさにいま思い描いていた者の声音がすぐ傍で聞こえた。やましい考えを見咎められたような錯覚に動揺し、手にして
いたテキストを取り落とす。
舌打ちとともに屈み込めば、通路の曲がり角から祐希の背中越しに柔らかな気配が近づいてくるのが分かった。
「どうかしたのか」
気遣わしげな兄の声。「何でもない」とだけ言って、祐希は顔も見ずに歩き出す。昴治があっけにとられたのが解かった
が、敢えて振り向く事はしなかった。
暫しの逡巡のあと、
「夕べはありがとな」
心許なげに昴治は言った。それきり踵を返したらしい足音を確かめてから、祐希は足を止め小さな背中を目で追った。
講義でなく総括課の実務中である兄の両腕には、形も大きさも多様なファイルが山と積み上げられていた。
「あんた、今日早番だろ。晩飯に何か予定は?」
弟からの問いはそれ自体も内容も、昴治にとってみれば思いがけないものであったろう。「別に何も・・・」と答えたその表
情は、狐にでもつままれたように途方に暮れている。
「俺の方が実習5時上がりで早い。終わったら連絡しろよ」
決め付けも甚だしい台詞を言うだけ言って再び歩き出した祐希の背に、戸惑いながらも承諾の返事が届いた。
後ろ手で諒解の合図を返し、今度こそその場を歩き去りながら、祐希は改めて苦い笑いを噛み締めることになった。
おそらくは---いや、間違いなくあの兄には解かってなどいないだろう。何故祐希が今朝黙って部屋を出たのか、聞きも
しない昴治のシフトを言い当てることが出来たのか、など。
自分ばかりが懸命になっている現状が何やら腹立たしくもあり、
(ばか兄貴が---今夜は少し、驚かせてやる)
余りにも一方的な「仕返し」を胸中で算段しつつ、祐希は夕食の為の予約を入れるべくIDカードを取り出した。
祐希が解からない。
いや、実のところはここ5年くらいずっとそうであるのだけれど。
夕べといい今日の昼間といい、何だか体よくからかわれている感は否めなかった。
(普通に接してると思えば、急に無愛想になったり。かと思えばすごく歩み寄ってきたり・・・ホント、訳分かんないよ)
もともと祐希は猫のように気紛れな性質だった。それでも仲違い前のあの頃は、少なくても昴治に対してだけは従順で
あったから、ここまで振り回された経験もない。
(いちいちあいつの気ままに付き合ってやることも、ないのかもしれないけど・・・)
ものすごく幸せそうな顔してる、と満面の笑顔の親友に茶化されたのは朝食の時だった。何でもないと言っても認めな
いイクミは、最初からその理由が「夕べ祐希と穏やかな時間を過ごせたこと」であるのを看破していたに違いない。
ひと目で分かるほど上機嫌だったのかと思えば、昴治としてはバツの悪さの極みであったが、確かに弟との距離が少し
でも縮まったという実感に心は躍っていた。
ベッドの中での突然の抱擁や、朝一言もなく置き去りにされたことを差し引いても。
けれど。
就業終了のコールを聞きながら自問自答の中、自分のデスクの端末をおとしていると、
「相葉さん、用意いいですか」
向かいに座る同僚がそわそわとした様子も露わに覗き込んできた。
「・・・何の?」
「何の・・・って、月一恒例の飲み会じゃないですか!今回はフライトアテンダント課有志との合同でしょ!相葉さんがセ
ッティングしてくれたのに、忘れてたんですかっ」
首を傾げる班長を呆然と見下ろして、同僚は情けない声で抗議し始める。それを聞きつけた他の男どもまでが、顔色を
変えて2人のところに飛んできた。
「あー」と気の抜けた声を返し、昴治は面倒臭げに溜息をついた。
忘れていた。総括課の親睦のための飲み会---という呼び名の食事会である。何しろ乗組員の9割は未成年だ---を月
に一度行うようにしていたのだが、圧倒的に女子の少ない部署ゆえに、以前から逆に女子ばかりのフラアテ課との所謂
合コンを希望する者が多かった。
自分たちの班長とフラアテ課班長であるあおいとの親しさに、そんな男子課員が目をつけぬはずはなく、幾度もの押し
問答の末やむなく今回限りを条件に、昴治は幼馴染みに頭を下げ今夜の催しにこぎつけたのだ。
本気で半泣きになる後輩たちを宥めつつ、昴治は義務を果たすべく立ち上がった。
(俺にはどうでもよかったから、すっかり忘れてた。でもまあ、会場も押えてあるし別に問題は・・・)
ある。大有りだ。
今度は昴治の顔色が変わる番だった。脳裏に浮かぶのは不愉快げに顔を歪め、罵倒を吐き捨てる弟の姿。
完全なブッキングだ。当然どちらかを断るしかないが、なし崩しにせよ幹事となっている飲み会に出ないわけにもいかな
いだろう。先約である上、あおいに対しても顔がたたない。
(あいつ・・・怒るかな---怒る、よな・・・?)
胸ポケットから取り出したIDカードを見つめ、昴治は不意に湧き上がってきた奇妙な感情に自分で躊躇した。
約束を反故にすることは、理由はどうあれ祐希をないがしろにするということだ。もちろんプライドの高いあの弟はそんな
仕打ちに憤るだろう。けれどその腹立たしさの中に、ほんの少しでも「残念さ」を感じてくれるだろうか。
一緒に過ごせないこと自体を惜しんで欲しい。
そう考える胸の奥で、昴治の中の何かが甘く疼いた。それはこれまで受けたことのない、鈍い痛みを伴っていた。
「相葉さん、早く〜」
気の逸ったオトコどもに背中を押され、昴治は連行されるように事務所を後にした。掴む暇のなかった、自分の内に生ま
れ始めた「何か」に後ろ髪を引かれる想いを残して。
![]()
![]()