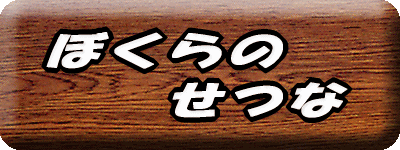
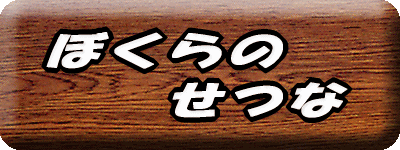
世論に悪名高い、かの「リヴァイアス事件」から早2年。
昴治ら初期搭乗者---正しくは事件の被害者たち---が、政府より是非にと請われて件の艦に再乗艦してからは、約1
年が過ぎようとしていた。
その悪名とは裏腹に、クルーの中にはいまだ一般大衆に人気を博している者たちがいた。事件の際リヴァイアスと400
余名の実習生を守るため尽力したとされる実習生トップグループ「ツヴァイ」の面々と、実質的に戦闘の矢面に立ったと
いう「英雄」たちである。
「この中から適当に何通かチョイスして、幾つか質問に答えるように---って・・・それマジな話っすか」
呼び出された会議室のデスクに積み上げられたメモリチップには、1つにつき約50通ものメールが収められていると
いう。ウンザリとした表情を隠すことなく副艦長であるユイリイに向けるイクミを始めとする、人気者宛のファンレターが。
その数、推定5000通以上。
先日火星に寄港した際、しかつめらしい顔で視察だと艦内を覗き歩いていた、軌道保安庁の現地支部のお偉方とかい
う連中が、生真面目な様子で指示と共に置いていったものらしい。が、
「ヴァイア艦については、やっぱりあくまで国家機密扱いなんでしょ。なのに一般向けの広報誌を発行するなんて、一
体何考えてんですか。オトナの皆様は?」
「ええ、そうよね。ただでさえ忙しいリフト艦担務ですもの。気持ちはよくわかるわ」
イクミの渋面に、向かい合ったユイリイも苦笑を禁じえない。
軌道保安庁の指示の概要はこうであった。
件の事件で公となった「ヴァイア計画」だが、勿論その全貌が公開されたわけではない。素人ではその理解の範疇を
超える難解な問題であるし、なまじな玄人に介入される惧れも、これまでの研究を悪用される危険も皆無とはいえなか
ったからだ。
とはいえ計画が公的機関のものである以上、大衆の評は良いに越した事はなかった。そうなれば、幸い---折角有し
ているメディア向きな恰好の題材をイメージアップのPRに使わない手はないだろう。
そこで考案されたのが広報誌と銘打ったPR誌---有体にいえば、著名な乗組員の記事をメインとした所謂「アイドル
雑誌」であり、目の前に積まれたチップこそ、そこに掲載するべく募集されたクルーへの質問付きファンメールなのだっ
た。
普段の明るい言動から受ける印象ほど、イクミはいわゆるミーハーなノリを好む性質ではない。何にせよ義務を疎かに
することを良しとしないから、それが計画推進のために必要だと言われれば遂行するに吝かではないけれど。
「祐希じゃないけど・・・ホント、俺たちは芸能人じゃあないっての」
最寄のチップの1つを指先で摘み上げ、「リヴァイアス第一の英雄」たる操船課班長は大きく深い溜息を吐いた。
「・・・本当にごめんなさい---でも、お願い。協力してもらえないかしら」
何の罪もないユイリイに手を合わされては、これ以上の愚痴も気が引けるところだ。
やれやれと頭を掻きながら、イクミは隣に座ってこれまで無言でユイリイとの遣り取りを気の毒げな顔で聞いていた親
友に視線を向けた。
「だって。どう?昴治としては」
いきなり話を振られ、2人分の眼差しを受けとめた総括課班長はキョトンと目を丸くする。
「俺?いや、どうって聞かれても・・・」
「ま、引き受けざるを得ないよな。大変だろうけど」
「ああ、そうだろうな---って、大変なのはユイリイたちツヴァイとかお前や祐希だろ?」
今度はイクミとユイリイが揃って目を丸くした。ワケが分からず双方を見比べる昴治に、溜息混じりに友人は言う。
「あのね、じゃあなんでお前がここに俺と一緒に呼ばれたと思うワケ」
「なんでって、呼ばれたから来ただけで・・・ずっと聞いてても、俺には関係なさそうだなあ・・・とは」
思ったけど、と困惑するばかりの昴治にユイリイが申し訳なさそうに口を開いた。手近のチップの中から数枚を選り抜
いて、
「これはほんの1部なんだけど、祐希くん宛のメールなの」
頓着なく昴治は頷いた。我が弟ながら祐希の人気の高さは、再出発前から身を持って知っていた。
「で、俺なりユイリイなりが今の事情を話して弟クンに協力を求める---と、どういうコトになると思う?」
ここへ来てやっと嫌な予感を感じ始め、昴治は露骨に眉を寄せた。
「・・・俺がやっても結果は同じか、もっと悪いと思う」
「またまたぁ!昴治くんたらご謙遜っ」
先程までの思慮深い班長の顔を棚に投げ上げ、イクミは普段のままのおちゃらけた態度も露わに両手で昴治の肩を
引き寄せる。馴れ馴れしいその手をはたいて、
「不適材だって!どうせならあおいかカレンさんに・・・」
「それが---その二人からの推薦でもあるの。相葉くんならどうしても彼がOKしてくれない時、代わりに質問に答えら
れるし・・・って」
ユイリイの言は援護射撃という名のクリーンヒットであった。
うんうん、と無責任に得心の頷きを繰り返す親友を睨めつけながらも、当局の決定の前に---正しくはユイリイの「お願
いモード」に完敗した昴治に、他の選択肢のあるはずもなかった。
かくして---自分宛てでもないメールの詰まった箱を両腕に抱え、昴治は弟の部屋へと出向くことになった。
地球にいた頃に比べれば格段に好転した---何しろ同じ部屋で寝起きしていても、殆ど会話さえなかった---とはいえ
いまだ気まずい知人程度という仲でしかない祐希が、一体何をどうしたら昴治の頼みなど、しかも大嫌いな部類の面倒
事を引き受けるはずがあるだろう。
それでも。
(引き受けたからには、仕方ない)
時間は午後8時前。祐希が日勤で、既にリフト艦から上がっているのは確認済みである。
深く大きな溜息を一つついて、昴治は目的地のインターホンを押した。
滅多にない早い帰りだった。
食事もシャワーもリフト艦のそばで済ませてきたので取り立ててする事もなかったけれど、根っから宵っ張りの祐希で
あるから、ではもう就寝しようか---などとは思いも及ばない。
ベッドヘッドに積み上げた音楽チップのてっぺんの一枚を携帯ドライブに差し込んで、時間潰しとばかり手近な雑誌を
手にベッドの上へと転がった。
その時、やはり滅多に鳴ることのないインターホンが来客を告げた。
訪ねてくる心当たりは3つしかない。
いまや本当の兄弟よりも姉弟らしい繋がりの幼馴染み、相棒を気取って憚らないV・Gチームの紅一点、そして兄の親
友を自称する所属課の班長だ。
もちろん素直に応じる裕希ではなく、彼らの方でもそれを熟知していたから、これで引き下がることは有り得ない。次に
打ってくる手でその内の誰であるかは限定出来るだろう。
(あおいなら出るしかねえか・・・後がウルセーから)
ところが続く反応は裕希の予想の範疇外だった。十数秒の沈黙のあと、再びチャイムが鳴ったのだ。ドアを挟んでい
てさえ分かるほど、躊躇った遠慮がちなコール音。
胸を過ぎった面影を裕希は慌てて否定した。そんなはずはない。いくら以前ほど険悪な関係でなくなっていようが、だ
からこそ今更、兄がわざわざ自分を訪ねてくるどんな理由があるというのか。
三度応答を請う音がして、裕希はとうとう立ち上がった。
これはきっとあのお調子者の仕業だ。兄を装って裕希を惑わせ、真に受けたところを揶揄う算段に違いない。だからド
アを開け、確かめてとっちめる。
(それだけだ、別にホントに兄貴が来たなんて思っちゃいねえ)
言い訳じみた独白に段々と腹が立ち、ドアを開けざま祐希は来訪者を怒鳴りつけた。
「うるせえ!いい加減にしろっ」
はたして---そこに立っていたのは、まさに兄---昴治本人であった。
思いもかけない邂逅に、双方が各々の心情でその場に凍りつく。二の句の告げない祐希より先に我に返ったのは、や
はり昴治の方だった。
「・・・悪い、疲れてるトコしつこくして」
少し顔を俯かせて兄は神妙に言った。その様子のせいか両手に抱えたダンボール箱が、大層重そうに祐希の目に映
った。
「別に・・・何か、用かよ」
いまの下らない失態も、自分が相変わらず兄にぞんざいな口をきいてしまうのも、全部アイツのせいだ---この場にい
ない「お調子者」ことイクミに八つ当たりの矛先を向け、祐希はバツの悪さに殊更仏頂面を作ってみせる。
「用っていうか、もし・・・お前がもし今少しだけでも、時間あったら---で、いいんだけど」
弱腰な台詞の割に、視線を戻して祐希を見る兄の眼差しは怖じけるふうもない。
「端末貸してくれないかな。ホントに、そんなに時間かかんないから」
祐希の胸に諒解と落胆の二色が混ざり合った。溜息を落しつつ、見れば兄の持つ箱には馬鹿げた数のデータチップ
が詰まっていた。
返事の代わりに半身を引いて入口のスペースを譲った。もう一度「悪いな」と呟いて入室した昴治は、ごく自然に相変
わらず散らかり放題の部屋を見渡し、ほんの一瞬何か言いたげな素振りを見せたけれど、特に小言を口に出しはしな
かった。
一年と少し前であれば、必ず言ったであろう---「たまには片付けろよ、だらしない」---言葉を。
作り付けのPCデスクに運んできた箱を置き、昴治はさっそくその中から一枚取り出したチップを端末に差し込んだ。
(よっぽど急ぎの仕事なんだな。よりによって俺の端末借りにくるなんて)
昴治の部屋からではライブラリーも所属の総括課も、ブリッジやあおい、尾瀬イクミの部屋までもが祐希のいるここを
経由する。
これまでの互いの行き来の頻度を省みれば、兄が祐希の部屋を選んだ最大にして唯一の理由が、ただ近かったから
であると考えるのは至極もっともなことだった。
ベッドに戻った祐希は、デスク前の椅子に腰掛け端末を操作する痩せた背中をぼんやりと見ていた。
幼い頃にはあれほど頼もしく思った、とうに自分より一回りも小さくなった背中を。
程なく、くるりと椅子を回して昴治は弟を振り返った。とっさに顔を逸らし損ね、正面から目が合った動揺のあまり祐希
は手にした雑誌を取り落とす。
そんな様子に首を傾げながらも、兄はやはりそれに触れる事無く、
「お前、ロングよりショートヘアの方が好きだよな」
「・・・はあ?」
あまりに唐突で場にそぐわない問いに、知らず間の抜けた声が洩れた。兄の物言いは質問というよりは寧ろ確認に近
いものだった。
「あれ・・・違った?」
弟の反応に驚いた昴治は、何故にか慌てて端末に向き直る。
「えっと、じゃあ---今まで行ったことのある場所で一番良かった街と、これから行ってみたいところ」
返答の代わりに祐希はベッドを降り立った。狭い個室であるから、隅に位置するデスクまででも僅か数歩で届く。兄の
肩越しに覗き見たモニターには、6分割したそれぞれの画面に表示されたメールと思しき文章の羅列があった。
トップ面の文書末に太字で書かれていたのは、「好きな食べ物はなんですか」---その下に赤で記されているのは
答えなのだろう、祐希の好物が幾つか並べて書いてあった。
次の面もその次も、ざっと見渡せば分かる---これは自分宛てのものなのだ。地球にいた頃から---あの救出劇以降
はより以上に---覚えのある、一方的に送りつけられ、すぐに目を通すことさえ止めて屑かごへ直行させていた、あの下
らない代物だった。
すでに書き込まれた「祐希への質問に対する答え」が、どれも的確に的を得ていたことに胸が疼き、同時に不思議な
思いがした。それを我が事のように記したのが、他の誰でもなく兄である事実に。
返らない答えを求めるべく再び振り返った昴治は、祐希がすぐそばに立っていたことにギョッとしたように身を竦め、次
いでその身体でモニタを隠すべく立ち上がった。
「いやこれは、その・・・」
「なんであんたがそんなモノの為にわざわざ---大体何で、あんたが持ってんだよ?」
ごく当たり前の切り返しに昴治はぐうの音も出ずに黙り込む。が、引くつもりが弟にないのをすぐに解したのだろう、素
直に事情を話し始めた。
「やっぱり・・・尾瀬の野郎か」
忌々しげに祐希がそう吐き出すと、
「イクミのせいじゃないって。当局とかいう、ヴァイア計画の関係者の都合っていうか」
慌てて昴治は友人を庇う。ますます弟の機嫌が下降していく理由が、自分のそんな態度のせいだなどとは少しも考え
及ぶことなく。
「---どけよ」
つっけんどんな声音で顎をしゃくった。気まずそうな表情で昴治は大人しく椅子から立ち上がる。空いた席に代わりに
座り込むと、祐希はまず始めに先程兄が誤解して訂正した答えを戻しにかかった。
「Q:ロングヘアとショートヘア、どっちが好き?」
「A:ショート」
「あ、やっぱり」と小さく呟きながら、昴治は弟の肩越しにモニタを覗いて来た。
あっという間にそのチップ分の応えを書き終え、
「終わりか。そっちのは?」
振り向きもせず言うと、一瞬兄が息をのむのが分かった。
「いや、まだ。じゃあ悪いけど---」
祐希が差し出した処理済のチップを受け取って、昴治はいそいそと次のものを選びにかかる。ちらりと盗み見た、その
嬉しげな横顔にまたも祐希の胸は騒いだ。
(こんなコト押し付けられて・・・そんな顔してんじゃねえよ、バカ兄貴)
たとえその気性から頼まれ事を断れなかっただけだとしても、いま実際に兄はここにいて祐希のそばで大層楽しげに
見える。
自分に都合が良すぎて、どこか夢の中のようにも思ったけれど---それならばそれでいい。今は少しでもこの「夢」を
長引かせることだけを祐希は願った。
問いの多くは取るに足りない、他愛無いものだった。が、
「Q:恋人にしたい好みのタイプを教えて下さい」
やはりありがちなこの問いに至ったところで、軽快だった祐希のキー操作はピタリとその動きを止めた。
「・・・コーヒーでも淹れようか。キッチン借りるな」
一瞬おりた沈黙のあと、はたと何かに心づいたように昴治は慌てて祐希から離れていった。所謂“こういった事”には鈍
いくせに気遣いに長けた兄が、何を考えたのかは手にとるように分かった。
(自分の目を憚って俺が書き渋ったとでも思ったんだろ・・・バカ兄貴)
祐希が幼馴染みの少女に好意を持っていた事を昴治は知っている。しかし救出後の地球できっぱりと失恋した事実を
知っているかは定かでない。
そのあおいは「事件」の終幕で昴治を選び、稚い甘い日々を経た2人は、やがて親友へとその絆を結びなおしたのだと
いう。
祐希はそれをとうのあおいから聞いていた。「祐希には私が話すって、昴治に言っておいたから」---だからノープロブ
レムよ!と言って微笑った彼女は、もしかしたら今の祐希の「本心」に気付いていたかもしれないが。
このままでいれば少なくとも肝心の兄に、「それ」が伝わることは金輪際有り得ないだろう。
人の部屋の慣れないキッチンで、おたおたする背中を肩越しに振り返り、祐希は重い溜息をついた。
祐希の中には現在、この「本心」を大切に想い叶えようとする自分と、気付いてしまったことを後悔し忘れようとする自
分が同居している。
特に意図しなければ、リヴァイアスの中で所属の違う兄と弟はそうそう顔を合わす機会もないから、離れている間は「
後悔」が優勢になりがちだ。それでもこうして傍にいて、姿を見て声を聞けば、やはり「本心」はどこまでも大きく強くなっ
ていった。
こんな自分はらしくない。
祐希は一度息をのんでから、モニタを睨み据え声を上げた。
「兄貴」
え、何---と当たり前に応える声に勢いをつけ、
「今夜、泊まれよ」
放ったままの問いに返事を打ち込みながら駄目を覚悟の返事を待った。
「Q:恋人にしたい好みのタイプを教えて下さい」
「A: K.A」
何時からか。
どうしてなのか。
考えたところで答えなど見つかるはずはなかった。
ただ、もはやどうにもならないくらいには---祐希は兄に、恋をしていた。
![]()
![]()