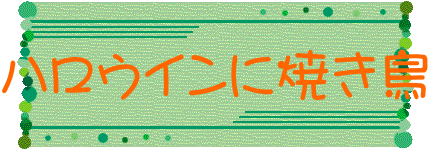
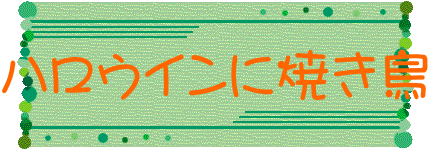
艦内標準時間であるところの地球暦10月31日。
今日も今日とて此処リヴァイアスでは、スフィクスネーヤと乗組員の
リンク率向上と銘打った、全艦上げてのお祭り──ハロウイン仮装ダン
スパーティが催されていた。
とはいえ主旨は常と変わらず大掛かりなだけの懇親会だったから、本
来の由来やルール、慣習などは二の次三の次。故にあちこちに置いたり
吊るしたりの装飾には、カボチャランタンだけでなく提灯やら星のオー
ナメントやらが混在している。
皆の格好もまたバラエティに富んでいて、モンスターや魔女や黒猫は
勿論、映画などのキャラクターを模した者、果てはメイドからバニーガ
ールまでいる始末だ。
そんな馬鹿騒ぎに用意されたブッフェメニューもまた、既製概念に囚
われることのない、見事なほど何でも有りなラインナップなのだった。
「・・・にしても、焼き鳥って」
保温の利いたプレートの上の一串を持ち上げて、相葉昴治は思わず含
み笑いを雫した。
総括課班長として今日も今日とて祭りの準備に大忙しの昴治だが、せ
めて当日の夕食くらいは人並みの時間にとって下さい、との課員らの厳
命を食らって会場の表に出たところである。
(飲食部門の企画にも目は通したけど。メニューの一つ一つまでは、
そういえば知らなかったなあ)
国名や料理名は定かではないが、似た形状や味付けの品は他に幾つも
あると聞く。
それでも、一口大の三切れの鶏肉の間に3センチ程の白ネギを挟み、
細い木串に刺して焼いたもの。これは紛れもなく日本の食文化の一端を
担う、昴治にも馴染みの深いアレだろう。
言うまでもなく今日という日には縁もゆかりもない料理である。とあ
る街の某相葉家を例外として。
串の半分を頬張って懐かしい触感を噛み締めた。焼き立てでないのは
残念だが、味はそこそこ及第点だ。
残りに齧り付き串から引き抜いた時、程近くに馴染みの深い気配があ
るのに気付いた。
「祐希」
視線を廻らせた先で予想に違わず弟の相も変わらずな仏頂面を見る。
かつて幾度も死を覚悟したこの黒い艦に、再び搭乗してから早4年が
経つ。
二度と返らないやもと諦め掛けた兄弟の繋がりは、春に根雪の下から
顔を出す新芽のように、ゆっくりと穏やかにその形を取り戻していった
ものだ。
無論のこと何もかもが幼い頃と同じではない。仮に兄弟が昔通りの接
し方を望んだとしても、当時を知る幼馴染みを筆頭に知人友人の満場一
致で──「いい歳した男同士が見苦しい!」──ダメ出しを食らったろ
うけれど。
「こんなとこで油売ってていいのかよ」
隣に立った弟がぶっきら棒に言った。
一見咎めるような物言いは、忙しさに感けて寝食を疎かにしがちな兄
を案じるが故だと、今の昴治にはよく知れていたから、
「ついさっき裏から出てきたとこなんだ。食事がてら休憩に行けって
言われてさ。お前、今日は日勤だよな。もう上がれたのか?」
くすぐったい気持ちで笑いかけた。祐希は一瞬珍しい生き物でも見た
ような顔をして、何故だかばつが悪そうに明後日の方を向きながら肯い
たものだ。
「肉、食えよ。肉」
(仮称)焼き鳥を2本一緒に持ち上げながら、最近の習いとなった決
まり文句を弟は口にする。
「ちゃんと食ってるって。ほら」
手にしたままだった串を得意げに掲げた昴治に、操船科のエースは呆
れ顔で鼻を鳴らした。それっぽっちで威張るな、と言外に腐された気が
して、些かの悔しさに知らずむっと唇を引き結んだ。
幼馴染みや親友にまで食の細さを日々説教されている身の上である。
せめて弟にくらい昴治なりの努力を認めてもらいたいと思っても罰は当
たるまい。
兄の膨れっ面に気付いてか、
「魚のフライ食うだろ。タルタルソースの」
祐希は独り言のように言いながら踵を返した。
食べ物の不満を食べ物で懐柔する気かと呆れる反面昴治の機嫌を直そ
うと祐希が自ら動いたこと、何より好物を覚えていてくれたことが素直
に嬉しかった。
だからだろう、
「祐希、トリキュウ・ワ・トリドン!」
考えるより先に口をついて出ていた。とある街の某相葉家でだけ、そ
れは一年に一度のお約束の言葉だった。
兄の「要求」に弟はぴたりと足を止めた。振り返るでもなくその場で
数秒立ちつくし、次いで向かう方向を少々変えて再び歩き出した。
ハロウインパーティをしましょう!ほら「鳥久・は・鳥丼」よ!
ふたりがまだ仲違いをする前の数年間。
10月の末日になると、母は決まって駅前の焼き鳥屋からテイクアウト
の丼を3つ抱えて、普段より心持ち早い時間に帰宅するやそう言ったも
のだ。
言わずもがなハロウインの決まり文句の捩りだが、当時の昴治らにこ
の「ハイクオリティな駄洒落」が通じた訳もない。
当然頭から信じ込み──今の祐希なら「トリしか合ってねえよ!」く
らいの突っ込みはしただろう──数年後には大変居た堪れない思いをす
ることになったという、イタい想い出付きの言葉だけれど。
ほどなく戻ってきた弟の手にはカレー用と思しき白い皿が乗っていた。
その上に鎮座するのは茶碗一杯強はあるほかほかライス。もう一方の利
き手にはスプーンと、どこかに麺類でも用意されているのかプラスチッ
ク製の箸を握っていた。
昴治の隣に、正確には(仮称)焼き鳥のプレートの前に立ったが早い
か、相葉家のサラブレットはスプーンで掬った「たれ」をライスの上に
振り掛け始めた。
5回ほどそれを繰り返し、またぞろ2本串を取る。箸で串から抜いた
肉とネギをライスに乗せれば、相葉家限定ハロウインのご馳走の出来上
がりだ。
丼ならぬカレー皿とスプーンを昴治の手に押しつけながら、
「トリしか合ってねえし」
ぼやくように祐希は言った。それが照れ隠しなのは明白で、先刻の連
想の見事な的中も相まって、昴治は敢えて堪えることなく笑い出す。
「何が可笑しいんだよ」と眉を寄せるくらいはするかと思った祐希は、
またも小さく驚いた表情を見せ、次いでお絵描きを褒められた内気な子
供の顔で下唇を噛んだものだ。
焼き鳥と白ネギとライスとを一緒に頬張って、懐かしい定番メニュー
を味わった。
「旨いよ、祐希」
同じように掬ったスプーンを祐希の口に近付けてみる。こんな人目の
有る場所で、流石に無茶振りかとは思ったけれど。
「・・・ばか兄貴」
天の邪鬼でやさしい自慢の弟は、乗せたものを落とさぬようやんわり
と、それでも標準装備の仏頂面を忘れることなく、兄の手から自身の用
意したスプーンを受け取った。
今は遠い故郷の惑星、その東の小国で。
とある街のとある家族の内でだけ交わされた、それは年に一度のごく
ささやかな、稚く温かなお約束だった。