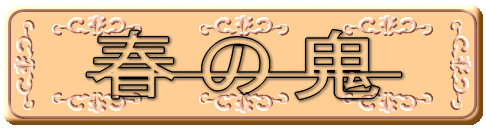
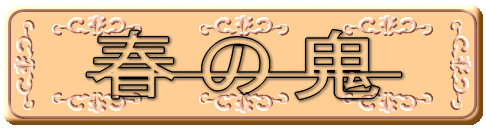
「日本の文化 立春の前日 節分の豆まき」
教壇の液晶ボードにそう書き込んで、若い担任教師は今ではあまり一般的
ではない行事について、7つの生徒らにも分かるよう、自分の子供時代の体
験談を用いながら話し始めた。
興味深げに聞き入る同級生の中でひとり、相葉祐希は耳を塞ぎたい思いを
懸命に堪えている。
その「現在は一般的でない」豆まきは、たった三人きりの相葉家にとっての
恒例行事であった。
それは祐希がもっとずっと幼い頃から仕事が忙しいと家を空けてばかりの母
が、ここ数年これまでの埋め合わせのように、何やかやと催す年中行事の内
の一つだ。
ありがた迷惑。
祐希の語彙がもう少し豊かであったら、今の心境をそう評したに違いない。
年末年始や誕生日、クリスマスはもちろんのこと、バレンタインに四季の祭り、
端午の節句、ハロウイン、お月見、はてはエイプリルフールに至るまで、催事
は忙しなく繰り返された。
もっとも幼い祐希はただそこにいるだけで、実際に準備をするのも楽しむの
も後片づけまでも、ほとんどは母と、そしてつき合わされ振り回される兄の昴
治だったのだけれど。
不器用ながら几帳面な兄が気忙しく立ち働き、それでも母との貴重な時間
を楽しんでいたのを知っているから、祐希は黙ってこの付け焼き刃の「家族
サービス」につきあっている。
それでも、この「豆まき」だけは別なのだ。
兄の次に大好きなあおいに毎年騙されるエイプリルフールも、母に無理矢
理奇天烈な服を着せられるハロウインも、チョコをくれただけの知らない人に、
兄が祐希にも見せないような笑顔を向けるバレンタインも嫌いだけれど、それ
よりもずっと。
今年もまた兄は、四苦八苦の態で役目の為の準備をしたことだろう。
それだから−−祐希は「節分」なんて、本当に大嫌いなのだった。
「三七度六分・・・」
昴治はぽつりとメモリを読み上げてから、青い色紙製の手作りの面を持つ手
で、体温計をケースに差し戻した。
目の前のベッドには布団に埋もれた弟が赤い顔をこちらに向けている。なん
とも申し訳なさそうな表情に知らず溜息が雫れた。
「まあ、しょうがないけど。何も今日熱ださなくてもいいのにな−−せっかく豆
まきする日にさ」
ホントついてないよな、という意味の言葉だった。責めるつもりなど毛頭なか
ったのだが、弟の目が見る間に潤み、昴治は慌てて布団の上に手を添えた。
「別に怒ったんじゃないだろ。兄ちゃんはただ−−」
「ごめん・・・なさい・・」
祐希のそれはすでに涙声になっていた。「勘弁してくれよ」と昴治は胸の内
にだけ呟いて、
「だから怒ってないって。泣くなよ、今日はお母さん早く帰ってきてくれるから」
宥めるつもりのこの台詞に、けれど祐希はまたも昴治の予想外の反応を返
した。
「−−おかあさん、やっぱりはやく帰ってきちゃうの?」
「うん、だって豆まきする予定だったから−−お前、帰ってきてほしくないの
か?」
母と弟の間がどこかぎこちないと思うことが希にある。そのたび昴治は気の
せいだと、自分に言い聞かせてきた。
否定して欲しいという兄の気持ちが通じたものか、
「そうじゃなくて」
祐希は勢いよく起き上がって言った。
「帰ってきたら、おかあさん豆まきするかも・・・」
「しないだろ。お前が熱出してるのに。仲間外れになんかしないって」
胸を撫で下ろしながら、昴治は弟の微熱に火照った身体を布団に戻そうと、
その小さな肩を押す。手に持っていたままだった手製の面が、くしゃりと曲が
った。それに目をやった祐希の顔が痛そうに顰められ、
「ホントに?おにいちゃんオニやらない?」
「は?」
「おかあさん、豆なげない?」
「お前・・・なに言って−−」
「だって、やなんだもん!おにいちゃんがオニやるのっ」
赤い顔をますます紅潮させて、祐希は声を上げた。瞳に盛り上がった涙が、
感情の高ぶりに呼応したように一粒こぼれ落ちる。
「−−おにいちゃんはオニなんかじゃ、ないもん・・・」
初めて豆まきをしたのは何年前だったか。まだ幼い息子たちの為に、豆とセ
ットで売られていた鬼の面を被ったのは母だった。
加減も分からない祐希と二人、家中母を追いかけ豆をぶつけた。
母は始終笑っていたが、その夜布団に入ってから、昴治はひどく後悔したも
のだ。
父が家を出たあの日−−母の涙を見たときに、自分が母とこの家を守るの
だと決めたのに。その母にたとえ遊びでも、豆を投げたりしてはいけなかった
のだ。
だから次の年からは、鬼をやりたいと自分から志願した。心配したほど豆の
衝撃は強くなく、使命感に駆られていた昴治にしてみれば、毎年の鬼の役な
ど本当に何でもないことだった、けれど。
「豆、ぶつけるの・・・やだ・・」
唇を噛みしめ堪えても、祐希の眦からは次々と涙が溢れ続ける。
「−−ばか祐希」
青鬼の面を床に落として、昴治は両手で弟の頭を抱き寄せた。ぶつかる勢
いでしがみついてくる祐希の、何時にも増して高い体温が切なかった。
「そんなにヤなら、なんでもっと早く言わないんだよ」
「・・・だって・・おにいちゃん、も、おかあさんも・・たのしそ・・だ、だから・・・っ」
ばかゆうき、ともう一度呟いて、昴治はそっと微笑んだ。
仕事から帰ったばかりの母が、喜んでこの古めかしい習いを行っていたは
ずがない。昴治にしても、自分たちとの触れ合いを大事にしようとしてくれる母
と、そんな時間を楽しみにしているだろう弟を喜ばせたくて、毎年巧くもない鬼
の顔を描き続けてきた。
「ほんと、ばか・・・」
「・・・ごめん・・なさ・・・い・・」
昴治の独白に、その兄の胸に顔を埋めたままの祐希のか細い声が応えた。
「にいちゃんも、な・・・ごめん、じゃないか。ありがと、だな」
「・・・なに、が・・?」
こっそりと持ち上げた祐希の顔は、涙でぐしょぐしょになっていた。普段の美
少年振りはどこへやら。思わず吹き出した昴治を見上げ、祐希はきょとんと目
を丸くする。
「なあ祐希、豆たべようか。いつもみたいに、自分のとしの数だけ」
「−−なげなくて、いいの?」
恐る恐るの問いに笑顔で頷いてやると、同じだけの笑顔が返ってきた。艶
やかな黒髪をすいて、今度は弟の全部を胸に抱きしめた。
腕の中から照れたようなくすくす笑いが聞こえる。
大丈夫。
昴治は安堵の息をつきながら、祐希の髪に頬を寄せた。
豆なんか投げなくても、うちには鬼なんかいないんだから。
もしそんなやつが現れたとしても、きっと−−。
「現在は一般的でない」豆まきは、たった三人きりの相葉家にとっての恒例
行事であった。
そうして祐希は「節分」なんかもそんなに悪くないかな、なんて思うようにな
ってきた。
何故って祐希のうちにはもうオニなんて来ないから。母の帰りをまって、縁
側から何もない庭へと豆をまく。それから兄の数えてくれる豆を食べる。
特においしいものでもないけれど、兄と食べるものなら祐希には何でもトク
ベツだから。
ちゃんと年の数の豆を食べると、早く大きく強くなれると母が言うから。
早く大きく強くなる。
そしてもしいつか、本当にオニがやってきてもその時は−−。
守ってみせる。
大切な温もりをくれるあなたを−−必ず、この手で。
拙いこの身の、すべてをかけて。
<END>
■このお話は、かつて(笑)リヴァイアス・オンリーイベントにて発行されました、
「桜三姉妹」くさか智さまの ちび兄弟アンソロジー「いつでもいっしょ」に
書かせて頂いたシロモノでございます。
「・・・ニュアンス2」後半をUPするにあたり、ここいらで再録しておこうと思
い立った次第です。
それにしても・・・祐希、別人にも程がある・・?(^_^;)